コンテナハウス完全ガイド!費用相場やメリットデメリット・固定資産税などをまとめて解説!

近年、住宅や店舗、オフィスとして人気が高まる「コンテナハウス」。以前は貨物輸送用コンテナを再利用するケースが多かったものの、日本の建築基準法に適合しないなどの問題がありました。現在では、JIS規格の建築用コンテナが登場し、安全性と快適性を備えた空間づくりが可能になっています。
一方、「ユニットハウス」は、コンテナハウスの多くが海外生産に対し、日本国内の工場であらかじめ生産されたモジュール型の建物で、設置や移設が容易なのが特長です。プレハブ建築の一種であり、短期間で施工できる点や、ユニットを組み合わせることで、広い空間を作ることも可能なため、事務所、店舗、倉庫、休憩所など幅広い用途で活用されています。
価格や住環境、維持管理ポイントなどのバランスを考慮しながら、コンテナハウスとユニットハウスの違いを詳しくご説明します。
コンテナハウスとは?

コンテナハウスは、コンテナを建築材料として活用した建築方法で、近年住宅やオフィス、店舗など幅広い用途で採用されています。強度や耐久性に優れた点が魅力ですが、安全な建築物として利用するには「建築専用コンテナ」を使用することが不可欠です。かつては貨物輸送用のISOコンテナを再利用するケースがありましたが、これらは建築基準法に適合せず、長期的な居住には適していません。
その理由として、まずISOコンテナは貨物輸送を目的とした設計のため、壁全体で荷重を支える構造になっています。そのため、窓やドアなどの開口部を設けると強度が著しく低下し、建築基準法が求める耐久性を確保できません。
次に、日本の建築基準法ではJIS規格の鋼材が求められますが、ISOコンテナにはこれが使用されていないケースが多いため、安全性に不安が残ります。さらに、ISOコンテナはJIS認定工場での溶接が行われていないケースも多いため、建築物としての品質基準を満たせません。
技術的にはISOコンテナを補強し建築基準法に適合させることも可能ですが、大規模な改修が必要となり、コストが大幅に上がってしまうため注意が必要です。
現在のコンテナハウスでは、JIS規格の鋼材を使用し、国の基準に沿って製造された建築専用コンテナが用いられています。これにより、耐震性や耐久性を確保しながら、開口部を設けても十分な強度を維持できます。コンテナハウスを建てる際は、単なるコンテナの流用ではなく、建築基準を満たした適切なコンテナを選ぶことが、長期的な安心と快適な住環境を実現する重要なポイントとなります。
コンテナハウスの費用相場
コンテナハウスは、低コスト・短工期で建築できる点が魅力ですが、実際の費用は仕様や施工内容によって大きく変わります。特に「コンテナハウスは安い」というイメージを持っている方も多いですが、建築基準法をクリアした建築専用コンテナを使用し、居住空間として快適に仕上げるためには、想像以上のコストがかかることがあります。そのため、計画の段階でしっかりと予算を把握することが重要です。ここでは、コンテナハウスを建てる際にかかる主な費用項目について解説します。
-
1. コンテナ本体費用
コンテナハウスには、建築基準法に適合した「建築専用コンテナ」を使用する必要があります。一般的な20フィートコンテナは1基あたり90万円前後~、40フィートコンテナは200万円前後~が相場と言われています。
-
2. 工事費(基礎工事・設置費)
コンテナを設置するためには、地盤改良や基礎工事が必要です。ベタ基礎や独立基礎を採用することが多く、費用は50万~150万円程度。コンテナの設置費用として、クレーン作業や固定作業が必要になり、20万~50万円ほどかかります。
-
3. 内外装費用
コンテナハウスは断熱性や防音性を確保するため、内装工事が不可欠です。断熱施工、壁・天井の仕上げ、床材の施工などで坪単価50万~100万円が目安となります。外装についても、デザインによりますが、塗装やサイディング施工が必要になり、10万円~が一般的です。
-
4. 設備工事費(電気・水道・空調)
電気配線、水道・排水工事、エアコンや換気設備の設置も必要です。これらの費用は設備の仕様によりますが、トータルで200万~450万円ほどが相場です。
-
5. 諸費用
設計費用や建築確認申請費用、施工管理費などの諸費用も発生します。これらを含めると、50万~100万円程度が追加でかかることを想定しておきましょう。
まとめ
コンテナハウスの費用は、シンプルな仕様であれば総額300万~500万円程度、こだわった内装や設備を導入すると1,000万円以上になることもあります。安価に建てられるイメージがありますが、実際には建築基準を満たすための施工が必要で、思った以上に費用がかかるケースが多い点に注意が必要です。建築専用コンテナを使用し、適切な施工を行うことで、安全で快適なコンテナハウスを実現できます。
コンテナハウスのメリット

ここでは、コンテナハウスの主なメリットを3つ紹介します。
-
1. 短工期での建設が可能
コンテナハウスの魅力の一つは、建築期間の短さです。一般的な建築と異なり、コンテナハウスはあらかじめ工場で製造されたハウスを現地に運び、設置、接続作業を行うだけで済むため、現地作業が大幅に短縮されます。小規模なものであれば、1~3カ月程度で完成させることも可能です。特に、早期の開業や施設稼働を求められる事業用途においては、大きなメリットとなります。
※ただし、コンテナハウスは海外生産が多く、輸入までの時間とコストが想定以上にかかる場合があるため注意が必要です。
-
2. 高い耐震性・耐久性
コンテナハウスは、重量鉄骨造のため、非常に高い強度を持ちます。木造や軽量鉄骨造と比較して、耐震性や耐久性が向上しており、地震や台風などの自然災害にも強いという特長があります。鉄骨構造は、長期間にわたって安定した居住空間を提供し、しっかりとした強度が求められる施設にも対応できます。また、適切なメンテナンスを行えば、さらに長期間の使用が可能です。
-
3. 柔軟なデザインが可能
コンテナハウスはモジュール構造であるため、コンテナを組み合わせることでさまざまな間取りや用途に対応できます。一棟建てのコンパクトな店舗から、複数コンテナを連結した複合施設まで、自由度の高い設計が可能です。
このようにコンテナハウスは、短工期での建築が可能であり、強度や耐久性にも優れ、そして柔軟なデザイン性を兼ね備えており、住宅はもちろん、オフィスや店舗、宿泊施設など多用途に対応できる建築手法として注目されています。
コンテナハウスのデメリット

-
1. 断熱性の問題
コンテナは鉄骨造であるため、断熱性が低いという欠点があります。鉄骨は熱伝導率が高く、外気温の影響を受けやすい素材です。特に夏は高温、冬は寒さを感じやすく、冷暖房を効率的に使わないと室内が極端に暑くなったり寒くなることがあります。これを解決するためには、断熱材を追加する必要がありますが、これには追加コストがかかり、設計や施工に工夫が求められます。
-
2. スペースの制限
コンテナハウスは一般的に、サイズが2種類と限られており、広い空間が必要な場合、複数のコンテナを連結、積み重ねて使うことになりますが、これにより建設コストが増加する可能性があります。また、1つのコンテナだけでは十分な広さを確保できないことが多いため、スペースに制約があることを考慮する必要があります。
-
3. 搬入経路の制約と設置場所の制限
コンテナハウスは工場であらかじめ制作されたコンテナを現地に運搬し、クレーンなどで据え付ける方式が一般的です。そのため、現地での設置には大型トラックによる搬入と、それを吊り上げるための重機(主に積載型トラッククレーン)を使用できる十分なスペースが必要となります。設置場所までの道路幅が狭い・進入経路が曲がりくねっている場合などは車両が現地まで到達できず設置できない場合があります。また設置場所の周囲に電線・樹木・建物などの障害物がある場合にもクレーン作業が困難になり、搬入そのものができない可能性があります。
-
4. 固定資産税が高くなる可能性がある
コンテナハウスはしばしば「仮設的」なイメージを持たれますが、基礎を設けて設置され、用途が居住や事業用などの場合は、一般的な建物と同様に課税されるのが原則です。さらに建築用コンテナハウスは、JIS規格に基づいた重量鉄骨構造で作られることが一般的です。建物の固定資産税評価額は、主に構造(木造・軽量鉄骨・重量鉄骨など)や建物の用途・大きさ・築年数などに基づいて算出されます。重量鉄骨造は耐用年数が長く、評価額が高くなりやすいため、結果として木造や軽量鉄骨と比べて固定資産税が高くなる傾向があります。将来的な税負担も含めて長期的なコスト試算を行うことが重要です。
コンテナハウスに関するよくある質問
コンテナハウスの耐用年数は?
鉄骨造の建物には、鉄骨の厚みに応じた法定耐用年数が定められています。
※以下事務所用途の場合の法定耐用年数で、用途により異なります。
- 鉄骨厚3mm以下:22年
- 鉄骨厚3.1~4.0mm:30年
- 鉄骨厚4.1mm以上:38年
JIS規格に準拠した建築用コンテナハウスは、主に鉄骨厚6mm以上の重量鉄骨で作られることが一般的なため、法定耐用年数は38年ですが、適切なメンテナンスが行われている場合、40年以上の使用も可能とされています。
コンテナは通常、耐久性が高い素材で、外部環境に対して非常に丈夫に作られています。構造自体が非常に堅固なため、長い耐用年数が期待できますが、錆びや腐食のリスクなどもあります。
そのため、定期的なメンテナンスが必要で、防錆処理や塗装を定期的に行うことが重要です。その他に、地域の気候や環境によっても耐用年数は異なります。湿気や塩分が多い地域では、腐食が進みやすいため、特に防錆対策が重要となってきます。
コンテナハウスに固定資産税はかかる?
コンテナハウスが恒久的な建物として認定されるか、仮設の構造物として扱われるかによって、税金の取り扱いが異なります。
コンテナハウスが基礎を作り、構造的に安定した建物として使用される場合、その土地に建つ恒久的な建物として認定され、固定資産税が課されることになります。
一方、コンテナハウスが一時的な使用目的で設置されている場合(例えば、移動可能な状態で使用される場合や、短期間の仮設住宅として使用される場合など)は、固定資産税の課税対象外となることもあります。この場合、仮設物として扱われるため、固定資産税はかからないことが一般的です。
ただし固定資産税は、地方自治体によって異なるため、コンテナハウスの取り扱いも地域によって異なる場合があります。
コンテナハウスに建築確認申請は必要?

一般的に、コンテナハウスを設置する際には建築確認申請が必要になることが多いですが、具体的な要件は地域や使用方法によって異なります。
コンテナハウスが恒久的な住宅や建物として使用される場合、一般的に建築確認申請が必要です。これは、建物として使用する場合、日本の建築基準法に適合させる必要があるためです。
一方で、コンテナハウスが仮設住宅や一時的な住居として使用される場合(例: イベント会場の宿泊施設や仮設オフィスなど)は、建築確認申請が一部緩和される場合もあります。ただし、一定の規模を超える場合や、長期間使用する場合には、建築確認申請が求められケースが多いです。
申請を怠った場合、法律上の「違反建築物」となり、行政指導や是正命令、最悪の場合は使用停止や撤去命令が科されることもあります。建築確認を受けずに使用を始めることは法令違反となり、罰則の対象となりますので、必ず事前に確認し、必要な手続きを行いましょう。
なお建築基準法の適用は、地方自治体によって異なる場合もあります。そのため、コンテナハウスを設置する前に、地元の自治体や建築担当窓口に確認を取ることが大切です。
この他にも、既存の建物の用途変更を行う場合も建築確認申請が必要となるケースがありますので注意が必要です。
コンテナハウスの用途は?
コンテナハウスは、店舗やカフェ、オフィスなどとして幅広く利用されています。モジュール構造を活かして複数のコンテナを組み合わせることで、用途や規模に応じた柔軟な空間設計が可能です。
近年では宿泊施設や展示スペース、移動式の仮設拠点などにも応用されており、デザイン性と実用性を兼ね備えた建築手法として注目されています。
また、災害時の一時的な住居や、地域イベントなどでの期間限定施設としても活用される例が増えています。
頑丈で、環境に配慮した建物としても人気が高く、個人・法人問わず、多様なニーズに応える選択肢となっています。
コンテナハウスの住み心地は?
コンテナハウスは強度が高く、耐震性や耐風性に優れているため、住環境としても安心して利用することが可能です。
また通常の建物に比べて建設費用が抑えられますが、コンテナ自体のサイズは限られており空間的な制約があるため、広々とした空間を求める場合は複数のコンテナを組み合わせる必要があります。
外部の音が響きやすいことや、結露を引き起こしやすいこともあるため、防音対策や湿気対策を行うことも大切です。
コンテナハウスにメンテナンスは必要?
通常の建物と同様に長期間にわたって快適に住むためにはメンテナンスが必須です。
特にコンテナハウスは鉄製であるため錆びやすく、雨や湿気が多い地域では鉄の表面が腐食する可能性があります。防錆塗装は約3〜5年ごとに点検し、サビ発見時は早期補修が重要です。
また、色褪せ対策も含めて10年周期での全面塗装がおすすめです。屋根や窓枠など開口部のコーキングも劣化するため、5〜10年ごとに再施工が必要です。
また断熱性能が低いため、夏は暑く冬は寒くなりがちです。断熱材の劣化や、外壁の隙間からの空気の侵入が原因となることもあるため、定期的に断熱材の状態チェックを行うことが重要です。
コンテナハウスとプレハブ・ユニットハウスの違い
-
1. 施工期間
コンテナハウスは規模や仕様によりますが、設置から完成までおおよそ1~3カ月程度かかります。
ユニットハウスも同様にモジュール建築であり、短工期が特長です。現地での組み立て作業は最短1日で完了するケースもあり、全体の施工期間も1~3カ月程度と、コンテナハウスと同程度です。
※ただし、コンテナハウスは海外生産が多く、輸入までの時間とコストが想定以上にかかる場合があるため注意が必要です。
-
2. 可変性
コンテナハウスはモジュール建築のため、柔軟に増減築が可能です。ただしコンテナの壁や柱が、建物を支える構造体として機能しているケース(耐力壁など)も多いため、改修時には専門的な配慮が必要です。改修時にはコンテナ接合部の適切な気密・断熱・防水処理を行うことが重要で、正しく施工すれば長く安心して利用できます。
ユニットハウスも同様にモジュール建築ですが、コンテナハウスと比較し、より最小限の現場作業でスムーズに増減築や移設することが可能です。ボックスラーメン構造という柱と梁で建物を支える構造で、窓や壁はパネル方式を採用しているため、増減築や移設だけでなく、間取りの変更などの改修も容易に対応可能です。ユニットハウスは事業の変化に合わせて運用がしやすい点も魅力で、より高い可変性を重視する場合には、ユニットハウスやプレハブの選択が適しているケースもあります。
-
3. 耐久性
前述のとおり、コンテナハウスは鉄骨厚6mm以上の「重量鉄骨造」に分類されるため、事務所としての用途の場合、法定耐用年数は38年です。さらに、適切な防錆処理や定期的なメンテナンスを行えば、40年以上の使用も可能とされ、非常に高い耐久性を持ちます。
一方で、ユニットハウスは「軽量鉄骨造」に該当し、当社製品では鉄骨厚が3.2mmまたは4.5mmのため、法定耐用年数は30年または38年です。実際にはメンテナンス状況により、30~50年程度の使用も十分可能とされています。
いずれの建物も、工場で精密に製造されるため、品質が安定しており、環境に合わせた耐久性を確保できます。
※用途により法定耐用年数は異なります。
-
4. 設置場所
コンテナハウスとユニットハウス・プレハブ両方とも、設置が容易な半面、大きなトレーラーやクレーンを使用して運ぶ為、道路幅の制限や電線などの妨げを考慮する必要があります。
設置場所の土地が傾斜している場合、水平に設置するための費用が加算される場合もあります。
 三協フロンテアのユニットハウス製品一覧
三協フロンテアのユニットハウス製品一覧
プレハブ・ユニットハウスの事例5選
ユニットハウスは、短工期・コストパフォーマンス・柔軟性を兼ね備えたプロダクトです。工場で事前に製造された製品を現地で組み立てるため、施工期間が短く、最短1日で完成します。人手や時間をかけずに建物が完成するため、従来の建築方法に比べて全体のコストが低くなります。
またモジュールが統一されているため、設置後の増減築や移設が容易で、事業や用途の変化にもフレキシブルに対応可能です。
さらに、デザイン性も高いため事務所や倉庫だけでなく、店舗、教育施設、医療/介護施設、イベント時の一時的な建物など幅広い用途で活用されています。
このようにさまざまな特長があるユニットハウス。ここでは実際にユニットハウスがどのように活用されているのか、いくつか事例を紹介します。
クラブハウス
スポーツ科学総合センターのクラブハウスとしてユニットハウスをご利用いただいています。食堂やシャワー室、ロッカールームや会議室など、多くの選手・お客様が快適に過ごしていただける、様々な設備が整った施設です。外観はブラックで統一されており、全体的にシックな印象かつ、ルーバーパネルを組み合わせることで、よりオシャレな外観に仕上がっています。
https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1810




フードコート
のと里山空港にある復興支援者向け宿泊施設の、付属フードコートとしてご利用いただいています。定食屋やラーメン屋、カフェなどの飲食店のほかに、様々なサイズのミーティングルーム・ワークスペースもあり、多くのお客様にお立ち寄りいただいています。またガラス張りを採用いただくことで、明るく開放的な室内空間が実現できる他、夜には室内の明かりが際立つ、特徴的なデザインになっています。
https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1812




飲食店
開発中の駅前に建設する飲食店として、ユニットハウスを採用いただきました。鉄板焼きやお好み焼きを提供されており、内観は和の要素をふんだんに取り入れたおしゃれなデザインが印象的です。屋上にはデッキユニットを採用いただき、いずれは飲食スペースとしてご利用いただくとのこと。またガラス張りを採り入れることで、室内に自然光が差し込み、シックかつ穏やかな空間が広がっています。
https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1789




会社事務所
物流センターの事務所としてご利用いただいています。外観はモダンでスタイリッシュな印象を与え、周囲の環境とも調和しています。室内は、自然光が差し込む明るく広々とした空間が広がり、1階は受付事務所、2階には会議室、食堂、休憩室などが配置されています。またインナーバルコニーは、荷受けするドライバーが雨に濡れないよう配慮されており、実用性も兼ね備えています。
https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1813




ピアノ教室
保育園に隣接する、ピアノや英語の教育スペースとしてご利用いただいています。この物件は、不要になったユニットを回収、中古品として整備し、再利用する「リユースユニット」を使用した事例です。新品に劣らない清潔感やおしゃれな外観が印象的です。屋根や床などに防音対策が施され、近隣に影響なく利用でき、子どもたちがのびのび学習できる環境が整っています。また、小規模なスペースでも、ガラス張りやデッキを組み合わせることで、広々した空間を演出しています。
https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1785




まとめ
以上のことから、コンテナハウスとユニットハウス・プレハブはそれぞれ異なる魅力があり、比較的短期間で快適な住環境を整えることができるとして、注目を集めています。
ユニットハウスはご覧いただいた事例の通り、デザインや内装の選択肢も豊富なため、オリジナリティあふれる空間を実現することが可能です。また安定した品質と高い利便性が魅力のため、幅広い用途でご利用いただけます。
自分にとって最適な建築工法を見つけるために、それぞれの違いをしっかり理解し、慎重に検討することが大切です。
三協フロンテアのユニットハウス お問い合せ
お問い合せ デジタル
デジタル オンライン
オンライン LINEで
LINEで











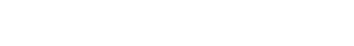
 お問い合せフォーム
お問い合せフォーム デジタルカタログ
デジタルカタログ LINEで質問
LINEで質問 オンライン相談
オンライン相談